
【DTM】ゴルトベルク変奏曲
ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲のゴルトベルク変奏曲は、グレン・グールド演奏のものがとても有名です。
この曲に初めて触れたのはグールドの1956年度盤です。
彼の演奏でこの曲が大好きになったのですが、演奏自体はわたしはあまり好きではありません。
彼のハミングが邪魔なところが一番の理由です。
アンドラーシュ・シフの演奏が好きです。
リチャード・グードやゾルタン・コチシュの演奏があったらぜひ聴いてみたいのですが。
【成り立ち】
正式な名称は「多様な変奏の付いたアリア BWV988 1741年」です。
不眠症に悩むカイザーリンク伯爵のために、バッハが「アリアと変奏曲」を作曲。
それを14歳のゴルトベルク少年が、夜な夜な演奏したという寓話から「ゴルトベルク変奏曲」という俗称がついています。
1741年に実際、バッハはカイザーリンク伯爵を訪問しています。
その事実から作られた俗称なのかもしれません。
現在では、クラヴィーア練習曲シリーズに統合される作品とみなされています。
クラヴィーア練習曲シリーズには
・前奏曲、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグ、メヌエット、その他の華麗な作品(パルティータ1~6) BWV825-380 1731年
・イタリア趣味を模した協奏曲(イタリア協奏曲)とフランス風の序曲 BWV971、BWV831 1735年
が含まれます。

基本的なコード進行は以下の通りです。
| G | D | Em | D | G | C | D | G |
| G | D | Em | A | D | G | A | D |
| D | G | C | B | Em | C | B | Em |
| C | G | C | D | G | C | D | G |
テンポの遅い変奏では、装飾のためのコード(sus4等)も多用していています。
変奏は第1番から第30番まで。
前後にアリアを置いて全部で32曲の長大な変奏曲です。
このアリアはバッハの奥様のアンナ・マグダレーナのお気に入りの作品だったようです。
【第31変奏】
第28,29,30変奏は”好きなように”を意味するクオドリベッドです。
第30変奏ではバッハも当時の流行歌を引用しています。
これを現代の人たちへのメッセージと解釈したわたし。
調子に乗って第31変奏を作ってみました。
ペンネームは”ちこべ”で書いています。
アリア→31変奏→アリアです。
DAWは”studio one 3 pro”です。
対位法はまったく考慮していません。
(というよりできませんでした)
真冬の早朝、寒風吹きすさぶ中撮った水鳥たちのかわいい仕草を御覧くださいませ。
(もっと重くてでかい三脚が必要だなぁと思いました)
バラエティに富んだ30もの変奏曲をバッハはどのくらいの時間で作ったのでしょうか。
PCやDAWどころか電気、電灯もない時代です。
その作曲している姿を想像しただけで、なんかもうありがたい気持ちでいっぱいになります。
【まとめ】
ゴルトベルク変奏曲、
聴き始めは「やっぱりイイなぁ、これ」
と聴いているのですが、
15変奏辺りから集中力がなくなり、
意識もなくなってきて、
気づくと最後のアリアだった、もしくは終わっていた、ということがよくあります。
だからグールド盤のハミングが邪魔と感じるんですね。
(気になって寝られないw)
聞き手に素晴らしい音楽を次から次へとたたみかけることで、神経と聴力を疲労させて睡眠へ導く
これがバッハの目論見だったのかもしれません。




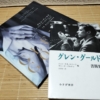


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません